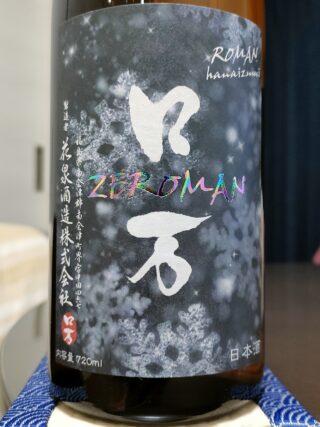「社会保障制度」を身近に感じてみませんか?「社会保険」の中から「雇用保険制度」を簡単に解説します。(Part1)

皆様こんにちは。以前のブログで、「社会保障制度」における4つの柱についてご紹介させていただきました。今回もその1つの柱である「社会保険」の中から、中身の1つである「雇用保険制度」について理解を深めていきたいと思います。
<雇用保険制度は「失業者」から「求職者」に変わるための保険になっています>
雇用保険制度と聞くと、「失業した時に備える保険」というイメージがあると思います。もちろん、失業したときの現金を保障出来る制度という側面がありますが、雇用保険の基本的な考えは、「次に働きやすくするための準備を保障する」という制度の作り方になっています。これは、日本国憲法に定められた国民の三大義務である「勤労の義務」と「納税の義務」を支える制度として理解していくと納得しやすいかと思います。失業状態でも生活がなんとかまかなえる状況を作り、更に次に働きやすい体制に移行しやすいような保障を行うことで、総合的に「働く」ということを支える制度になっています。働くことは生きることとも直結しているという、国の理念が具体化している制度とも言えますね。
雇用保険制度には「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と大きく4つの給付に分かれています。今回はその中から「求職者給付」「就職促進給付」についてそれぞれ給付内容を簡単にご紹介していきます。
最初は「求職者給付」について紐解いてみましょう。
<「求職者給付」は、失業した状況に応じて4分類され、それぞれ保障されています>
この給付には「一般被保険者」「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」という4つの対象者が想定され、それぞれに給付が存在します。
[「一般被保険者」が受給できる手当金は4種類です]
一般に、雇用保険をかけていた被保険者が失業状態となり、受給が可能になる手当金が4種類あります。
① 基本手当金
離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あり、7日間の待機期間を経て申請ができます。4週間に1回ハローワークでの求職活動(失業認定)が必要です。離職した日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の50~80%(60~64歳は45~80%)となっています。
② 技能習得手当
受給資格者が公共職業訓練を受ける場合に、基本手当金に加算して支給します。「受講手当」としては日額500円で、支給上限が40日です。また公共職業訓練に通う「通所手当」として42500円を限度として交通費も支給されます。
③ 寄宿手当
受給資格者が主な生計者の場合、公共職業訓練を受けるなどで同居家族と別居して寄宿する際には月額10700円が支給されます。
④ 傷病手当
受給資格者が離職して、ハローワークに求職の申込をした後に、疾病や負傷のために15日以上続けて就職出来ない場合に支給されます。30日以上引き続いて就業出来ない場合は、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長することも可能です。また、疾病や負傷のために「健康保険による疾病手当金」を受給されている場合は、雇用保険による疾病手当は支給されません。
[「高齢被保険者」として、65歳以上の方が失業しても雇用保険が適応されます]
高年齢被保険者とは、2017年1月1日以降、新たに就職した65歳以上の方で、所定労働時間が1週間に20時間以上で、かつ31日以上雇用が見込まれる方を指します。離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。
支給額は被保険者であった期間に応じて支給され、支給額は離職した日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の50~80%です。被保険者であった期間が1年以上だと、給付日数は50日分で、被保険者であった期間が1年未満の場合給付日数は30日分です。
上記支給要件を満たして支給される給付金を「高年齢求職者給付金」といいます。超少子高齢社会において、働き手が少なく定年延長が叫ばれている昨今において、働くことを社会貢献ややりがいに繋げていく方も多くなりました。雇用保険制度が活用出来れば、様々な形で「働きやすさ」を補う1つの方法になり得ると考えられます。
[季節的に雇用された方も「短期雇用特例被保険者」として雇用保険が適応されます]
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される方のうち、「4ヶ月以内の期間を定めて雇用される方」「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間以内の方」のいずれにも該当しない方を指します。簡単に言えば、いわゆる出稼ぎの方で雇用保険に加入している方です。
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。支給要件を満たして支給される給付金を「特例一時金」といい、基本手当の日額の30日分に相当する金額が支給されます。
[「日雇労働被保険者」に対しても雇用保険が適応されます]
日雇労働被保険者とは、日雇いの方、または30日以内の期間を決めて雇用される方を指します。失業前の2か月間に26日分以上の印紙保険料を納めた人に支給されます。納めた保険料により、支給額は3等級に分かれており、1級が7500円、2級が6200円、3級が4100円で、それぞれの等級の13日から17日分の支給になります。上記支給要件を満たして支給される給付金を「日雇労働求職者給付金」といいます。
次は「就職促進給付」について紐解いてみましょう。
<「就職促進給付」には、「再就職」を支える方法がそろっています>
・この給付には失業した方の「再就職」を支えるための手立てとして現金給付を行っています。
・給付内容としては「就業促進手当」「移転費」「広域求職活動費」「求職活動支援費」です。それぞれ給付内容を簡単にご紹介していきます。
《就業促進手当(全部で4種類)》
1、再就職手当
基本手当の給付日数を残して再就職した方へ給付されます。
2、就業促進定着手当
再就職手当を受けて、6ヶ月以上雇用されて離職前の給料よりも低い場合に、低下した分の6ヶ月が支給されます。
3、就業手当
基本手当の給付日数を残して、再就職手当の対象とならない常用雇用以外での就業をした方へ支給されます。
4、常用就職支度手当
基本手当の給付日数を残した就職困難者が就業した場合に支給されます。支給額としては、早期に再就職した場合の再就職手当は、給付日数を3分の1以上残した場合は、基本手当日額×60%、3分の2以上残した場合は基本手当日額×70%、その他は基本手当日額×30から40%となっています。
《移転費》
・ハローワークから紹介された職業に就くために、またはハローワークから指示された公共職業訓練などを受講するために、現在の住所や住まいを変更する必要がある場合は、受給資格者本人とその同居家族の移転に要する費用が支給されます。
・移転費は「交通費(鉄道費、船賃費、航空費、車費)」「移転料」「着後手当」の3種類です。移転日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへの申請が必要です。
《広域就職活動費》
・ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、「交通費(鉄道費、船賃費、航空費、車費)」「宿泊費」などが支給されます。
・ハローワークから広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に、ハローワークへの申請が必要です。
《求職活動支援費》
・2017年1月1日から就職面接のための子どもの一時預かり費用などの求職活動に伴う費用が支給されるようになりました。
今回は雇用保険制度における4つの給付の中から「求職者給付」と「就職促進給付」にポイントをしぼりご報告させていただきました。次回は「教育訓練給付」と「雇用継続給付」について触れたいと思います。