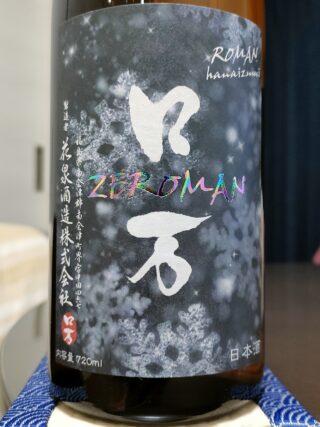自分の気付きと振り返り(49)「ソーシャルワーカーの仕事は感情労働だと意識する」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分に引っかかった事を自分の言葉を追加して、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「ソーシャルワーカーの仕事は感情労働だと意識する」というものです。

この言葉は、ソーシャルワーカーの新入職をした方に必ず伝えている事の1つです。対人援助職は、日々様々な「人の間」で仕事をしていきます。そこには、必ず情報や感情が関わる人の分だけ存在します。それらの感情に触れて、自分を通して出た言葉を相手に伝えていく事を仕事では繰り返していきます。
私たちが一日の中で対応するクライアントの数は一人ではありません。予定している面接の方はもちろんの事、突発的に相談に来る方なども当然あり、一日で複数の対応が重なることが日常です。その他電話やメールやオンライン通話など、様々なコミュニケーション手段をクライアントやケースに合わせて柔軟に変化させて対応もします。
このように、コミュニケーションを武器とするソーシャルワーカーの仕事は、クライアントと構成メンバーに対して、常に頭と心で入力(インプット)も出力(アウトプット)も使い続けていきます。限られた時間と制度と構成メンバーの中で、ケース事態の難易度も大きく変わります。仕事が重なるほどに、分単位で優先順位をつけ続ける判断も求められます。これら仕事の蓄積は、ふとした時に疲れとしてしっかり実感していきます。上手くいったケースなら自分としても達成感はありますが、上手くいかなかったケースならなおの事疲労感は自分を包み、モヤモヤとしたままになってしまう事が多くなります。
これらモヤモヤを感じる事も含めた頭と心の疲れは、ソーシャルワーカーとして仕事をするまで、私は意識した事がありませんでした。身体も疲れているのだけれど、それより頭と心が疲れた変な感覚になるのです。この感覚を知ったからこそ、私は新入職のスタッフには、一日の終りに心のわだかまりは職場に置いていくために「吐き出してみよう」と自分の心の言語化を促しています。これにより、自分の感情労働を自分自身が認めて、言語化の練習に繋がりながら振り返りや気付きにも繋がる内容だと考えています。
自分の気持ちを言葉にするのは苦手だった私ですが、今は昔よりも意図的に「まずは思った事話してみますね」と切り出していけるようになりました。考えた事ではなくて感じた事を話せる「心理的安全性」が確保できる場作りや仲間作り、職場作りも重要です。
仕事の終りに「今日も感情労働にしっかり励んだね、お疲れ様でした」と自分自身や仲間に言ってあげられる私でいたいと思いました。