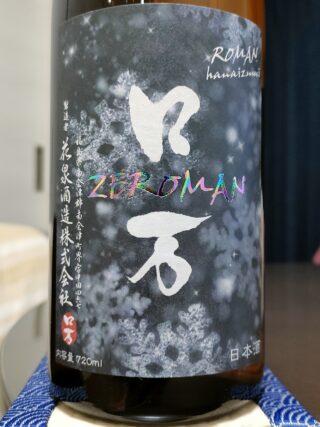自分の気付きと振り返り(51)「分かっているような気にならない」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分に引っかかった事を自分の言葉を追加して、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「分かっているような気にならない」というものです。

ソーシャルワーカーは仕事上、クライアントはもちろんの事、チームメンバーも含めた関わる人達を常に「アセスメント」していきます。アセスメントは、情報を収集・分析・統合・判断の総体として行う対人援助職の技術の1つです。
アセスメントが少しずつ上達していくと、アセスメントした人のことを分かったような気がしてしまいます。もちろん、アセスメントにより、その人の特徴や考え方、思い至る事、行動原理など、妥当性のある推定は出来る所があります。しかし、アセスメントをした事で私自身がその人を分かったような気になってしまうと、「決めつけ」という主観になってしまい、他の見方をシャットアウトしてしまう事があり、失敗した経験が私にはありました。
それは後から考えるほど非常に怖い経験でした。なぜなら、自分が決めつけてしまったが故に、アセスメントをした人が自分の予想の範疇を超えた対応や行動をとった時に、「何故?」と思うと同時に、「自分のアセスメントが間違っているはずがない」と責任転嫁してしまう事に繋がったからです。
私もそうですが、人は多面体です。私が仕事上見えている事は、あくまでも多面体の中の一定程度の部分でしかありません。いくらアセスメントをしたからといって、「その人の全てが分かる」なんて、おこがましいものです。そして、人は変化していく生き物です。それ故、その変化に対してもアセスメントしていくのであれば、私たちは「常に分かろうとし続ける事」しか出来ないのだと思います。
アセスメントをしていく対象者に対して、一定程度の解像度が高くなっていくと、私はすぐわかった気になってしまう癖があります。今回改めて「人は他人に見せていない部分が必ずある」「人の気持ちの全ては分からない」という当たり前の事を思い出し、それでもソーシャルワーカーとして常に「人を分かろうとし続ける」態度は持ち続けていきたいと振り返りました。