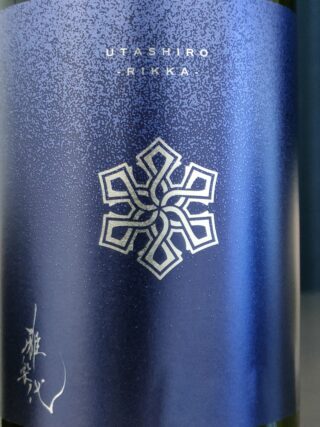自分の気付きと振り返り(52)「本人の思いを聴くと動ける」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分に引っかかった事を自分の言葉を追加して、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「本人の思いを聴くと動ける」というものです。

対人援助職の仕事は、クライアントとその家族にまずは出会う所から始まり、思いや言葉を交わしながら人となりを知り、ニーズを掘り起こし、それを共有しながら解決の出来る社会資源に繋ぐ仕事です。しかし、一方で、私自身が直接クライアントに会わず、関係者からの依頼で動くことも多々あります。
例えば緊急性の高い受診の相談や手配が代表的です。これは、他者のアセスメントを自分に落とし込み、迅速に動くことを優先しているため、本人に会わないで行動に移せる状況です。この対応は、自分としても特にモヤモヤを感じる事が少ない少ないのです。
一方で、命に関る緊急性の高くない状況で、クライアントではなく所属組織の緊急性の高さのみで動くように急かされる環境下で、他人のアセスメントを鵜呑みにして動く行動は、自分としてモヤモヤを感じていきます。このモヤモヤの正体は、クライアントを中心に置いているかどうかの違いだと考えます。
所属組織のあるソーシャルワーカーは、「クライアントの利益」と「組織の社会的な役割と利益」の折り合いを付けていかざるを得ない状況にもあります。これがよくある「板挟み」です。私も新人の頃からよく板挟みにあい、自分が傷つくことを恐れるあまり、所属組織の言葉のみを絶対として、組織に対して交渉する事もせず動いてしまう経験を非常に多くしてしまいました。
その結果、早く結果を出さなければいけないと焦るあまり、他者のアセスメントのみで動いてしまいました。これは、自分のモヤモヤを助長させ、かつクライアントの信用も無くす行動でした。とても徒労感の多い残念な体験です。
そんな経験から、板挟みにあう新入職のソーシャルワーカーには、私の自戒も込めて「本人の思いを聴くと動ける」ということを伝えています。傾きかかったソーシャルワーカーとしての立ち位置を立ち止まって見直し、クライアントの思いを聴くことで、クライアントを中心に据えるポジショニングに引き戻します。そして、何よりクライアントの思いを聴くことで、自分のソーシャルワーカーとして行動する原動力を取り戻させてくれると実感しています。
自分として、しっかりとしたアセスメントの時間が取れない場合もあります。それでも、自分がソーシャルワーカーとして動きにくいというモヤモヤやひっかかりが生まれた時は、クライアントが見えない時だと私は思います。最低限必要なアセスメントに達しなくても、断続的でも想像して動けるようにするには、私は一目でもクライアントに会って、なるべく言葉を話せる状況なら言葉を交わすようにしています。
本人を根拠に動ける私を作る為に、その5分の行動をケチらないようにしていきたいと思います。そして、それが大切だよと仲間にも伝えていこうと振り返りました。