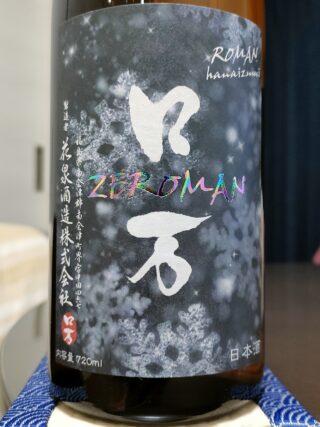自分の気付きと振り返り(80)「命の扱い方」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分の心に留まったもの、自分の振り返りの言葉などを取り上げて、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「命の扱い方」というものです。

医療や福祉の現場に身を置いて働いていると、経営側の視点として「数」の話を意識する事が多くあります。例えば、施設基準を満たす為の様々な「人員配置数」を始め、「基本報酬」や、国が主導している上位の「加算」を取る為の満たさなければいけない「平均在院日数」や「看護必要度」や「医療区分」等を、経営者側は日夜気にしていきます。それらの「数」を気にしていく事で、より多くの「収益」を得る事が目的になります。
社会保障制度の枠組みの中で経営している医療機関や福祉施設や事業所は、他の収益構造を持てない事が多く、利益の最大化を図る為には「顧客を集める」「空いているベッドは早く埋める」という事に注力しています。安定した収益が無ければ、私達も安定した給料をもらう事が出来ません。企業として収益を求める事自体は当然の動きではあるのですが、近年その動きが顕著に感じます。近年社会保障制度の枠組みで経営している医療機関や福祉施設や事業所は、大規模な法人を除き、本体収益が全国的に赤字となる状況が続いています。そして、全国的に倒産や廃業を余儀なくされる状況に陥っています。
人口ピラミッドからも分かるように、日本は超少子高齢社会です。全体的に働き手は少なく、他産業よりも給与面で見劣りする部分が多い医療機関や福祉施設や事業所は、原資が社会保障制度上決められているので、賃金上昇をしたくても一足飛びに上げられません。今の体制を最低限維持する為にも「人員」を補う事をする他ありません。人材派遣会社や人材紹介会社の高い紹介料が経営を圧迫している部分が多くなると、未来に向けて「人材」に投資出来る余力が無くなります。
この悪循環により、企業は一層「数」を求め、組織の評価基準が「数」になっていきます。そうなると、結果的に割を食うのは「患者さん・利用者さん」などの「顧客」になってしまいます。
実際に私が直近で経験した例をあげてみます。
この患者さん(表記上「Aさん」とします)は、腎臓の機能が悪く、全身の機能も悪化傾向で低空を維持している状態でした。食事や水分摂取量も少なく、意識はあるものの反応は鈍く、特別な医療処置はしておらず、バイタルサイン上は問題が無いという状況です。入院主治医から、現在の本人の状況としては「入院を継続している必要性は無い」という判断を出していました。その考えは変わる事が無く、私と家族は本人の安楽な暮らしを考え、最終的に介護施設を選び、様々な段取りを踏み入居(退院)に至りました。その間ご親族は、自分たちの時間をどうにか工夫して、Aさんへの面会時間も減らしながら入居対応に向けて動いておりました。入居(退院)の頃には、ご本人との明確な言葉のコミュニケーションは取れなくなっている状況でした。
病院にとってAさんが退院出来たという事は、「ベッドが空く」という「減収」にはなります。しかし「在宅復帰率」という数値が上がり、医療機関が満たさなくてはいけない数値に寄与します。施設にとっては空いているベッドが埋まる為「入居数」が増え「増収」となります。
しかし、Aさんは、1週間で再入院となりました。最終的に腎機能の急激な悪化で、入院後3日でお亡くなりとなってしまいました。
このAさんの再入院と死亡退院という一連の流れは、病院にとって入院に至ったため「ベッドが埋まる」という「増収」と同時に、短期間で病院と施設にとっては「ベッドが空く」という「減収」になります。数値でのみ評価をされて行くと、結果的に短期間の増減は出たものの、最終的にベッドが空く「減収」ではあるため、経営的には次の顧客になり得る方を見つけ。その方々にサービスを提供するべく対応していきます。
数で見ればAさんの入退院の流れは「1の増減」という、それだけの話になって終わってしまいます。でも、その「1の増減」の当事者だった「Aさん」と「ご家族」の命と暮らしと思いと時間を考えると、私はやはり物悲しさを感じてしまいます。もっと言えば、「心の通わない数だけで見たくない私」と「経営も含めて考える組織に属している私」の「ジレンマ」で「辛いな」と感じてしまいます。
私のこのジレンマは、大なり小なりこの仕事に携わっている方は感じている気持ちだと思います。医療機関や福祉施設や事業所が、ちゃんと社会インフラとして機能を保ち、よりよいサービスを提供していく為に収益の確保はもちろん大切ですし、決して稼ぐことを否定しているものではありません。
ただ、ちゃんと社会保障制度の枠組みで稼がせてもらう事をするなら、大前提として、私達は高い倫理観をもとにし、「命の扱い方」を考え、決して命を軽んじてはいけないと改めて思うのです。「Aさん=1の増減」とだけ捉えるなら、社会福祉士やソーシャルワーカーは世の中に要らないのかなと個人的に感じます。
今後益々、社会保障制度の枠組みの中で経営している医療機関や福祉施設や事業所は、人材不足と経営の悪化で淘汰されていく事が予想されます。私の勤めている組織ももちろん例外ではありません。
このような社会情勢下で、最終的に顧客から選ばれる組織というのは、多くの縛りの中から上手に社会保障制度を顧客のニーズに結び付け、人の命をちゃんと扱える人が多く在籍している組織なのかなと思います。そして、私はそうであって欲しいと願っています。
この様な私の感じたジレンマについて、見ないフリにする事無く改めて振り返る事が出来たAさんとの出会いに、心から感謝したいと思います。