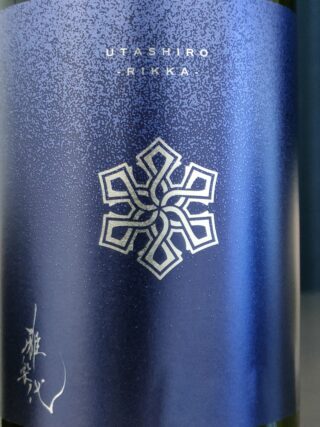自分の気付きと振り返り(81)「拗ねて機嫌が悪い自分を認める」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分の心に留まったもの、自分の振り返りの言葉などを取り上げて、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「拗ねて機嫌が悪い自分を認める」というものです。

私は幼少期から、周りの大人が求める子供像を察して過ごす事が多くありました。「大人びた子供」や「子どもっぽくない子供」の部分がありました。その反動からか、ひとたび自分の機嫌が悪くなると、あからさまに態度に出たり、相手に冷たくあたったり、不快感を振りまいたりと、感じが悪い子供でした。
そして、機嫌が悪くなると、どうにも機嫌が直らないのです。とりわけ他責思考が爆発し「こんなに我慢強い私を怒らせた相手が悪い」となるのです。同時に「感情を爆発させて相手に嫌な奴だと思われて恥ずかしい」とも思うので、自分から「さっきはごめんなさい」なんて言えません。相手から「感じ悪くさせてごめん」と相手に機嫌を取ってもらうまでが自分のシナリオだったのです。なんとも私はめんどくさいですね。
幼少期の特徴は、大人になった今でも私の癖で残ってしまっています。理不尽を押し付けられていると感じた時や、自分の価値観の中で許せないと思ってしまった時は、相手を責めてしまいます。そして、相手が私に不快感を与えた責任は取ってもらわないといけないと思い、相手を傷つけてもいいと感じてしまうのです。このように相手を責める私の行動について、私自身は自分のやっている行いを正当化します。
昔は、この正当化も気にならなかったのです。しかし今は、「正当化しようとしている自分」にひっかかり、気が付くようになってきました。気が付き始めると、自分のやろうとしている行動が、短絡的だったり、感情的だったり、昔の感情を引っ張り出して上乗せしているだけだったりと、気付くことが多くありました。そして、一呼吸置いた後、もう一歩自分自身に踏み込んで問いかけてみるのです。
「私は拗ねているだけなんじゃない?」「拗ねて機嫌が悪くなっているだけじゃない?」と。
「拗ねる」を辞書で調べてみると、下記のように説明がありました。
・ひねくれて強情を張る。
・片意地をはる。
・不平不満があって素直に人に従わず偏屈な態度をとる。
正しく私が正当化しようとしている自分の姿にぴったり当てはまります。他の方には「自分で自分の機嫌が取れるようにすると関係性が拗れず良い」なんて言った事もありますが、私はまだまだ拗ねる人間だったと気が付かされました。
当たり前なのですが、大人になった私は、自分が拗ねても機嫌を取ってくれる人はいません。それどころか、仕事の場面でそのような状況を見せると、信頼関係を失う事で直接的に自分に不利益が出てしまいます。それは、今までの自分の仕事ぶりや対応を見てくれている人の信用を無くす行為に繋がります。
自分という乗り物を上手に乗りこなす為には、自分の特徴を理解していく事が必要なのだと思います。それが対人援助職としては「自己覚知」という言葉になると思います。今回自己覚知出来た、拗ねる私の存在を否定する事無く上手に扱う為にも、その第一歩として「拗ねて機嫌が悪い自分を認める」という事から始めて行こうと思います。