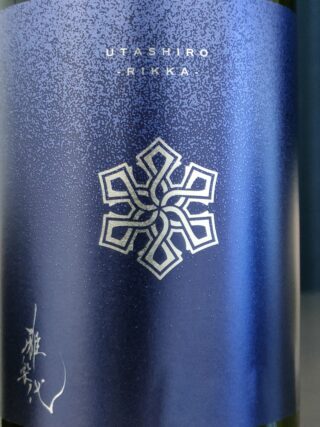自分の気付きと振り返り(85)「あなたは誰の支援者ですか?」

日頃の仕事での気付きや、本やメディアなどの言葉で自分の心に留まったもの、自分の振り返りの言葉などを取り上げて、備忘録的に書き留めます。
今回の言葉は「あなたは誰の支援者ですか?」というものです。

心残りを作った私のケースを振り返ります。(ケースの内容は本人が特定されないように加工してあります)
【ケース概要】
Aさん(80代後半男性)は誤嚥性肺炎で入院し、元々の認知機能の低下から嚥下機能低下が進行しました。その場のコミュニケーションは可能ですが、基本的には拒否が多く、点滴ルートや酸素チューブなどはすぐに自己抜去します。痰吸引時はチューブを噛もうとしてしまいます。拒否が出来る元気がある事を考慮して、なんとか対応できる治療を入院期間中行い、症状は一時期改善しました。リハビリテーションでは、生活機能として実用レベルでは無いものの、指示誘導で杖歩行が出来る状況にまでなりました。
しかし食事量を増やしていく過程で程なく誤嚥性肺炎を入院中に再発しました。本人は呼びかけに開眼する時と反応しない時を行き来して、ふとした時に「早く、早く。」とかすれながらの声を発します。その言葉の意味を何度も問いますが、説明の言葉は無く、また「早く、早く。」と発するだけ。その後は目をつぶり寝てしまう状況でした。
そこで、医師からAさんの妻と遠方に住む息子に病状報告をすることになりました。妻は病院に呼び、息子はオンラインツールで参加しました。妻と息子が本人に声をかけながら面会をし、その場面から私もソーシャルワーカーとして立ち会いました。
病状報告の場面では、それぞれがAさんについての思いを口にしていました。そして、Aさんが口にする「早く、早く。」の言葉の意味合いについても、各々が触れていきます。
【医師】
・本人の状態は医学的に見ても老衰と考えられる状況です。今後積極的な治療は難しい。本人が嫌がっていた点滴や酸素や痰吸引など、どこまで続けて行くかを考えていく必要があります。
・血管が既に確保できる場所が限られます。積極的に点滴を入れるには、侵襲的な治療に同意を頂く必要があります。
・ご本人も「早く、早く。」とおっしゃる。意味までははっきりしないが、本人は医療行為が苦痛になっている部分を認める。十分頑張ったと考えても良いのかもしれない。
【妻】
・本人は自宅にいる時から、薬を出されても飲まないし、飲まないと体に障ることを伝えても飲もうとしなかった。食べようともしなかった。
・入院時に行った医療行為の拒否は凄かった。もう本人を苦しめないで欲しい。傷つけないで欲しい。何もしなくていい。
・本人が「早く、早く。」と言うが、早く楽にしてくれと言っていると思う。(涙ながらに話す)
【息子】
・何もしなくて良いのかなと、正直思う部分はある。しかし、母が決めた事であれば、それで良いと思う。
・本人の言う「早く、早く。」という言葉は何なのかはっきりしないが、多分私に「早く来い」と言っているのかなと思う?
・この状態では、とてもじゃないが家に帰れないし、母も大変。病院でお願いしたい。
この三者の思いを聞いていく中で、私は瞬間的に色々な思いが頭をよぎりました。そして、結果的に私がした行動は、三者が話をしていく過程に「口を挟まない」という事でした。
それこそが、今回私が後悔したことです。私が頭をよぎった事は下記の通りです。
【私が頭をよぎった事】
・本人の「早く、早く。」は、「家に帰りたい、だから早く迎えに来て欲しい」だったのではないか?
・妻が面会に来て帰ると「俺をどうするんだ?」という表現が出た事があった。
・しかし、今私がこの発言をすることで、三者の話し合いの方向性を乱すことにならないだろうか?
・私が「Aさんは自宅に帰りたいと願っていると感じる」といった所で、家族のマンパワーはそれを受け入れることは出来ない。
・本人の思いとして「家に帰りたい」を代弁したとして、それは方法論として叶えることは出来ないのは明白。
・仮にAさんの死後、残された家族は、今回の結論に対して「それでよかった」と思える要素を残しておくことも必要ではないか?
・今私が感じるAさんの代弁をすることは、残される家族の決心を揺らがせてしまう事にならないか?
今の私が、その時感じた考えや思いを言語化して上記のように振り返ると、「ソーシャルワーカーとして仕事をしていない」と改めて後悔しました。その後悔の根底が、今回とり上げた「あなたは誰の支援者ですか?」という自問自答の言葉です。
私は三者の話し合いの場面の中で、本人の代弁(アドボケイト)を出来ませんでした。対象とするクライアントのAさんよりも、残される家族に重きを置いたのです。面接の場面において、表現の方法を持てないクライアントの思いを蔑ろにした後悔は、とても重いです。改めて失敗をしたと感じています。
ソーシャルワーカーは、そもそもプロセスに責任を持ち、自己決定をしてもらう為の伴奏者です。私はあの病状報告の場面において、家族の思いが悲しみから決断に至る涙ながら表情を目の当たりにして、家族に引っ張られ過ぎてしまいました。
今であれば、表現の仕方を変えて本人の思いとして私が感じる言葉を伝え、それでも最終的な方法論と照らし合わせ「気持ちの折り合い」がつくまで振幅に付き添う覚悟をして向かいます。しかしその時の私は、私が発言する事による家族の気持ちの振幅を増やす事を恐れ、それに向き合う覚悟も無く逃げました。その事を後悔したのだと改めて振り返りました。
Aさんが教えてくれたこれらの事を、私は必ず活かさなければなりません。その覚悟をする為に、今日の言葉に残しておきます。
「あなたは誰の支援者ですか?」