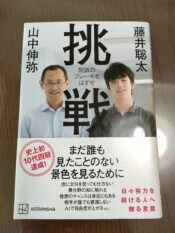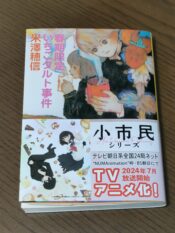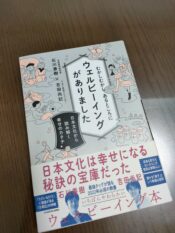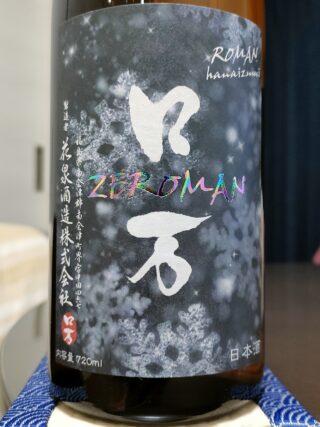本の感想(14)「バカと無知 人間、この不都合な生きもの」
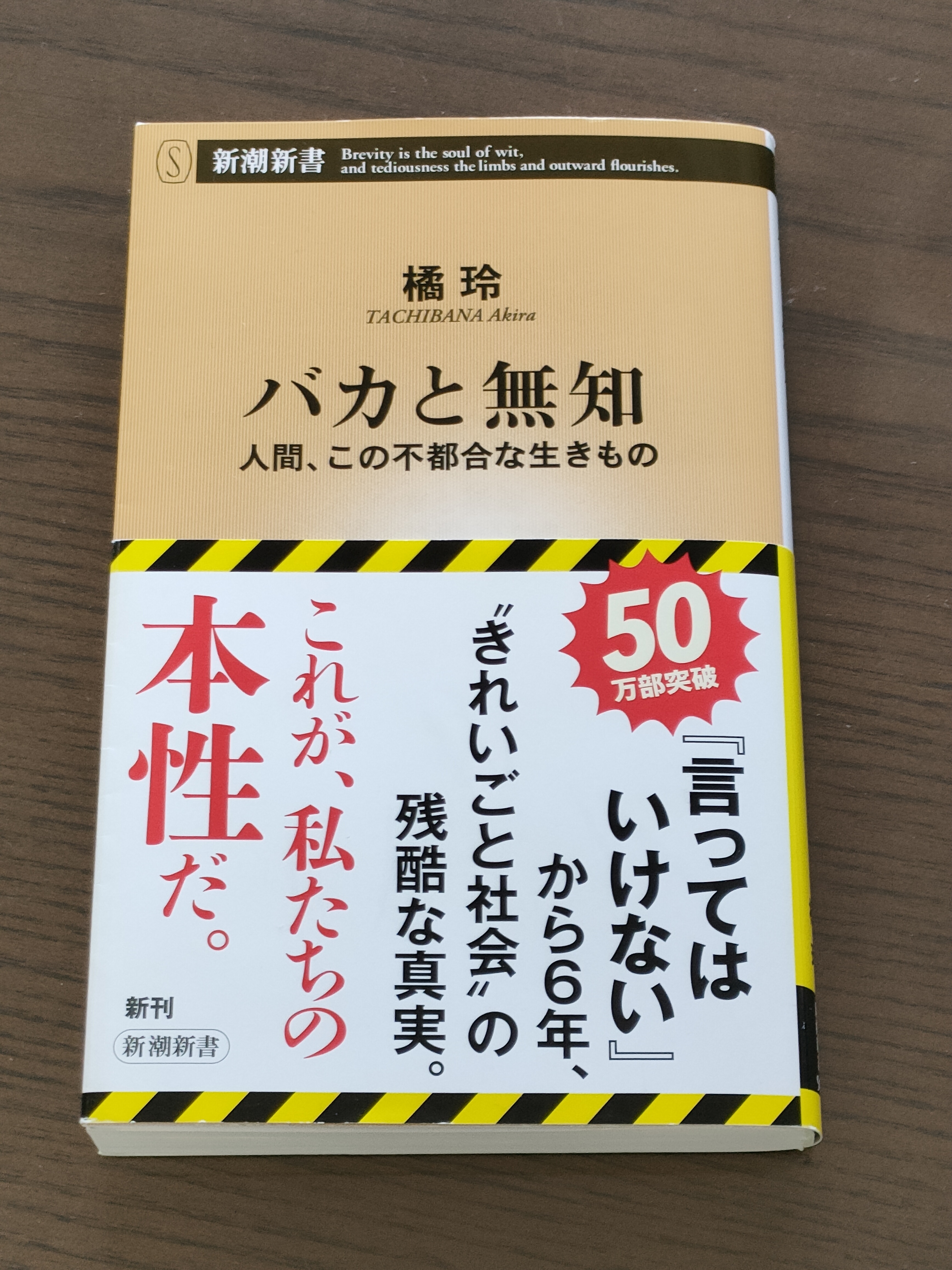
今回の本は、新潮新書から発行されている橘玲さんの著書「バカと無知 人間、この不都合な生きもの」という本を読んでの感想です。
著 書:「バカと無知 人間、この不都合な生きもの」
出版社:新潮新書
著 者:橘 玲
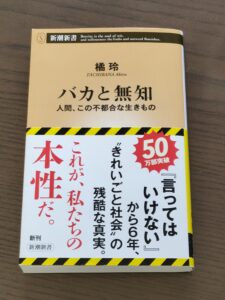
【感想】
「人間」という生き物の本性を読み解いた本というのが私の第一印象です。
人間という共同体の中で生き残る為に、知性を持ち、道徳や礼儀を備え、仲間から排除されない様に振る舞い、平和な「社会」を築き上げてきたのが私達人間です。
しかし私達は、旧石器時代からの基本OSに組み込まれている様々な「不都合」と取れる反応や言動を、今も引き起こしています。
現代社会においても、この旧石器時代の基本OSがアップデートされる事無く、根本的には「バカ」で「無知」な生き物なんだと読み進めるほどに痛感します。
この本を読んで私は、「人間は思った以上にバカな生き物だ」と思ったのと同時に、「私も自分が考えるよりもバカなんだなあ」と思えることで、色々と力が抜けて楽になれる所がありました。
人間の原初からの生存戦略的として備わってきているが故に表れている「いやらしさ」「醜さ」「残酷さ」「生き難さ」という「本性」が、この本を読むことで明らかにされる部分は多いのだと思います。
【印象に残った言葉】
・私たちの脳には極めて感度の高い火災報知器が備えられている。脳の警報機の過敏な初期設定は、旧石器時代は役に立っただろうが、現代のような「ものすごく平和で安全な社会」だとうまくいかなくなる。
・脳は良い出来事よりも悪い出来事を強く経験し、記憶するよう「設計」されている。
・徹底的に社会的な動物である人間は、不正を行ったと(主観的に)感じる相手に制裁を加えると、脳の報酬系が刺激され、快感を得るように進化の過程で「設計」されている。それに加えて下方比較を報酬、上方比較を損失と感じるから、自分より上位にあるものを引きずり下ろす事はとてつもなく大きな快感がある。
・この快感は、テクノロジーの力によって匿名のまま(なんのリスクも負わず)スマホをいじるだけで(なんのコストもかけずに)手に入るようになった。
・バカの問題は、自分がバカであることに気付いていないことだ。
・授業で理解出来たかテストして、その結果をフィードバックしても、この方法で学力を高められるのは認知能力の高い子供だけだ。こうした生徒は、自分が何を知らないかを知っているので、間違った所を修正して正しい知識に到達できる。
・認知能力の低い子供は、何を知らないかを知らないので、フィードバックを受け取っても、どうしてよいか分からない。
・認知能力が低い者が自分を過大評価する一方、認知能力の高い者が一貫して自分を過小評価している。何故そんなことが起こるかというと、ヒトは旧石器時代、自分に能力が無い事を他者に知られることは致命的だったから。
・優れた能力がある事を他者に知られることもまたリスクである。権力者が真っ先に排除しようとするのは、将来のライバルになりそうな有能な者だから。
・私たちは皆自尊心が低く(同調する)、同時に自尊心が高い(競争する)ように「設計」されている。自尊心が高い人をうらやましがるかもしれないが、自尊心が高い人は上手に装っている人だ。自尊心が高く同調性が全く人は、とうの昔に共同体から排除されるか、遺伝子を残すことが出来なかったから。
・圧倒的な強者からのアドバイスは(相手には序列を示す理由が無いので)、マウントと感じて自尊心が傷つく事は無い。ただ、両者の力関係が接近してくると、話はややこしくなる。序列が曖昧な時は、どんな機会も逃さずにマウントするのが進化の最適戦略だから。
・善意の名を借りて無力の人間をサポートする側に回ること(ボランティア等)は、自尊心の低い人にとって、自尊心を引き上げるもっとも簡単な方法である。
・誰が動画をアップするか分からないSNS時代には、失うものが多い富裕層ほど、品行方正になっていくのではないか。
・道徳の「貯金」ができると人は差別的になる。私達は無意識に色々な事を損得で判断し帳尻を合わせている。その帳尻合わせは「道徳」にまで及んでいる。
・現代社会の進化論では、ヒトが内集団に対してやさしくなることと、外集団に対して残酷になることは、コインの裏表である。仲間との絆は、仲間でもない者たちを排除し、限りある資源を確保するために進化した。
・まともな人は、なんの「生産性」もないSNSの論争(罵詈雑言の応酬)から真っ先に退場していくだろう。このようにして、まともでない人達だけがSNSに残っていく。人生に投下できる資源は有限で、まともな人は、その大半を仕事や家族、恋人との関係に使われるからだ。
・人間というのはものすごく厄介な存在だが、それでも希望が無いわけではない。一人でも多くの人が、「人間の本性=バカと無知の壁」に気付き、自らの言動に多少の注意を払うようになれば、もう少し生きやすい社会になるのではないだろうか。